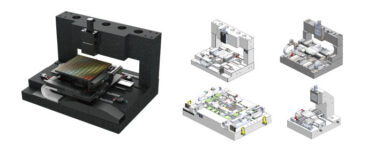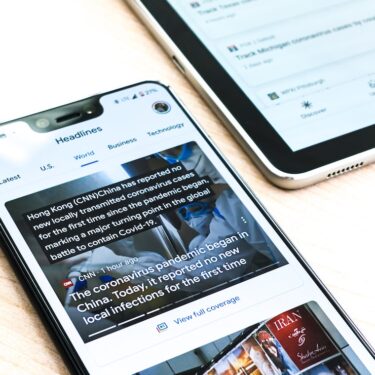先日、知人である社長が急逝した。誰もが43歳の若き社長の訃報に耳を疑った。彼は、本業以外に地域活動や地域産業発展にも尽力し、数々の団体の役職を務めていた。律儀な彼は、会合が重なっても少しずつ顔を出し少しも手を抜かず、先輩社長や取引先からも信頼されている人望の厚い若き名士であった。当然のごとく葬儀は社葬であった。弔問に行くと、1000人は下らない程の沢山の弔問客があふれていた。地元名士や数々の企業からの献花を受け、その間に長蛇の列をなして待った後、手際の良い係員に誘導されながら行う焼香は1回と決められていた。正面の写真を拝んだその一瞬、娘さんの泣きじゃくる姿が視界に飛び込んできた。もらい泣きしないよう、思わず視線をそらしてしまった。その一瞬がいわば故人への真の感情移入だったのかもしれない。
実はその数週間前に、別会社の専務取締役の弔問に行ってきたばかりである。
こちらは、前述の葬儀とは180度異なっていた。彼もまた急逝したのだが、葬儀は家族葬であった。通常、専務取締役のポジションでは社葬にするのが一般的だが、身内だけでしめやかに執り行われたのである。私は付き合いの濃さから特別に認めてもらったにすぎない。生前の彼は、前社長の時代から40年に渡って番頭役として会社を切り盛りしてきた人だった。しかし、現社長とは噛み合っていなかったらしく、双方から否定的な声があがっていたのは否めない。いろいろ察すると恐らく本人が家族葬を希望したようである。したがって、会社関係の人間は葬儀を知らされず、事後報告が一斉に回ってきた。現役でかつ40年会社に忠誠を尽くし大番頭をしていた役員の急死の葬儀は、どう執り行うのがよかったのだろうか。
会社が、「ぜひ社葬にさせてくれ」と申し出たにもかかわらず家族が拒んだのか、「家族に任せよう」と申し出なかったのかはわからない。しかし、会社関係者に少しも知らされなかった事後報告が業界に異様に映ったことは、紛れもない事実である。私が喪主だったら故人の遺言を聞き入れず、社葬にして立派に40年の仕事を全うさせてあげたかもしれない。彼の会社への貢献が多大であっただけに、長い付き合いの関係者にとっては誠に切ない限りである。
「俺が死んだら密葬にしてくれ」とか「粉骨にしてまいてくれ」とか言う人が結構いるようだが、果たして本音なのだろうか。前者のような弔問客の多さは、故人の生前の社会貢献や人徳を物語っており、“生き様"も読み取れる。しばらく疎遠になっていた人達であっても葬儀場で会えるのは、葬儀とは何よりも優先される人生の祝典だからだ。ただ、社葬の場合によくある血縁関係でない弔問客の中には、遺族への義理のため、利害関係の継続のため等の目的も含まれるのに対し、密葬は故人を本当に偲んでくれる人のみ集まる葬儀であることは言うまでもない。
「死んでまで、お義理はいいよ」とひっそりと散るのか、人生の幕を大喝采で閉じるのかは、その故人の立場に応じて喪主と会社が一緒に決めるべき重大な幕引きであろう。いくら遺言とて、故人の希望通りがいいものかどうか、今でも答えはわからない。
少なくとも会社は、少数でも「偲ぶ会」を企画するなど何らかの対応を図るべきである。
死んだらすべて終わりなのではない。故人の記憶はそれぞれに刻み込まれ、一周忌、三回忌と、何十年も故人を忘れさせないのである。私は今流行りの「遺言書キット」を買ってみた。社員が退職前に引き継ぎをするのと同じように、引き継ぎは文書で残しておかなければ無責任であり、問題が生じやすいからだ。人はひとりで生まれるが、死ぬ時はひとりの問題ではない。特に社会性のかかわりを持つ私たちは、自らの幕の引き方を考えておかねばならないと感じた。
(シュピンドラー株式会社
代表取締役シュピンドラー千恵子)

 オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。
オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。