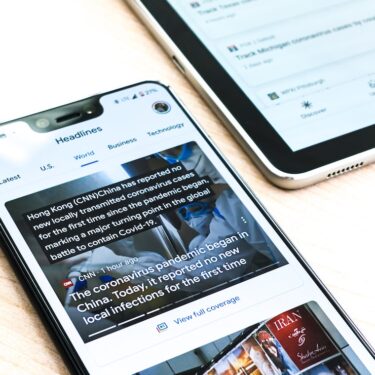18世紀から19世紀初頭に生きたイギリスの哲学者ベンサムは「最大多数の最大幸福」という功利主義の思想を説いた。18世紀の中頃からイギリスで産業革命が始まったと言われている。ベンサムは産業革命で沸騰している社会に生きた人で、それまでの世界とは様変わりし、物質的に豊かになっていく半面、都市に集まる人々の貧困ぶりと格差を目の当たりにして、この思想に行き着いたのだろう。
「最大多数の最大幸福」とは、簡略して言えば幸福とは個人的快楽である。個人の総和が社会であるから、最大多数の個人が最大の快楽を享受することこそ人間の目指すものだという思想である。近代に生きたベンサムが現代の先進諸国を見たら「最大多数の最大幸福」を達成した社会と評価するだろう。
ベンサムの思想を現代流に解釈すれば、経済成長で大いに沸いている新興国は物質的に豊かになっていく途中で格差が大きい社会であり、日本は沸騰した成長段階を脱して格差の少ない、落ち着いた成熟社会の段階にある。成熟社会とは成長した社会の踊り場であって衰退に向かうのか、ゆっくりと上昇に向かうのかを熟慮している踊り場的社会とも言えるのである。成長期では物事が量的に拡大してきた。量的拡大を求めなくなった成熟社会がスローに上昇するには、今までとは異なった質を求めていくことになる。
日本の社会は成熟社会の仲間入りをしている上に少子高齢化社会に入っている。年々若者の人口が減少しているから物の流れの量的拡大は止まり、減少していく傾向にある。したがって経済的には一応、現状を良しとして甘んずればいずれ衰退への軌道に乗ることになる。それを誰もが望んでいないことは日本のお家芸である物づくりの現場に表れている。物づくりの現場ではいかにコストを下げるか、いかに品質をつくり込むかで日夜、戦い続けているからだ。
現代に通ずる物づくりの歴史をみると、成長前期にはコスト競争に打ち勝つため、土地が安く労働賃金の安い地方へと工場を展開していった。その結果として地方経済は豊かになり、日本全体の活力につながった。成長中期以降になると物づくりの量的拡大が進んでさらなるコスト追求と品質の向上のため、地方に分散していた工場の大型化や分散していた工場をマザー工場に集約させて技術のシナジー効果を狙った。つまりコスト追求の方法を、低い労賃から技術向上に舵を切ったのだ。
この時点ではFAという言葉が生まれるほど工場設備がオートメーション化し、部品や機器営業にとって日の出の勢いが続いた。昭和の時代が終わると、すぐに様相が変わって円高がやってきた。
技術によるコストの吸収は無理と判断した物づくり企業は、再び労働賃金の安いアジア諸国に工場を移転させた。アジア諸国に活気を生む火つけ役を果たしたのだ。半面、国内では社会が成熟化し、物づくりの熱気は薄れ、長い間成長期の踊り場にいる。成長するアジア諸国もいつまでも低賃金の状態にいるわけではなく、国内でもいつまでも踊り場にいることはできない。
ここに地産地消という言葉がある。農水産物を作った産地で消費するという意味である。産業の物づくりではとにかく安く、高品質で、という流れで突き進んできた。ここらで地産地消という考えを参考にした物づくりも一考の余地があると思う。
とにかく安く、高品質にしなければ負けるという物づくりはグローバルな社会のものであり、スローな成長を目指すローカルな社会では地消するユーザーに合った物づくりを地産に合った技術でやることも大いに必要になってくる。
(つづく)
(次回は7月23日付掲載)

 オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。
オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。