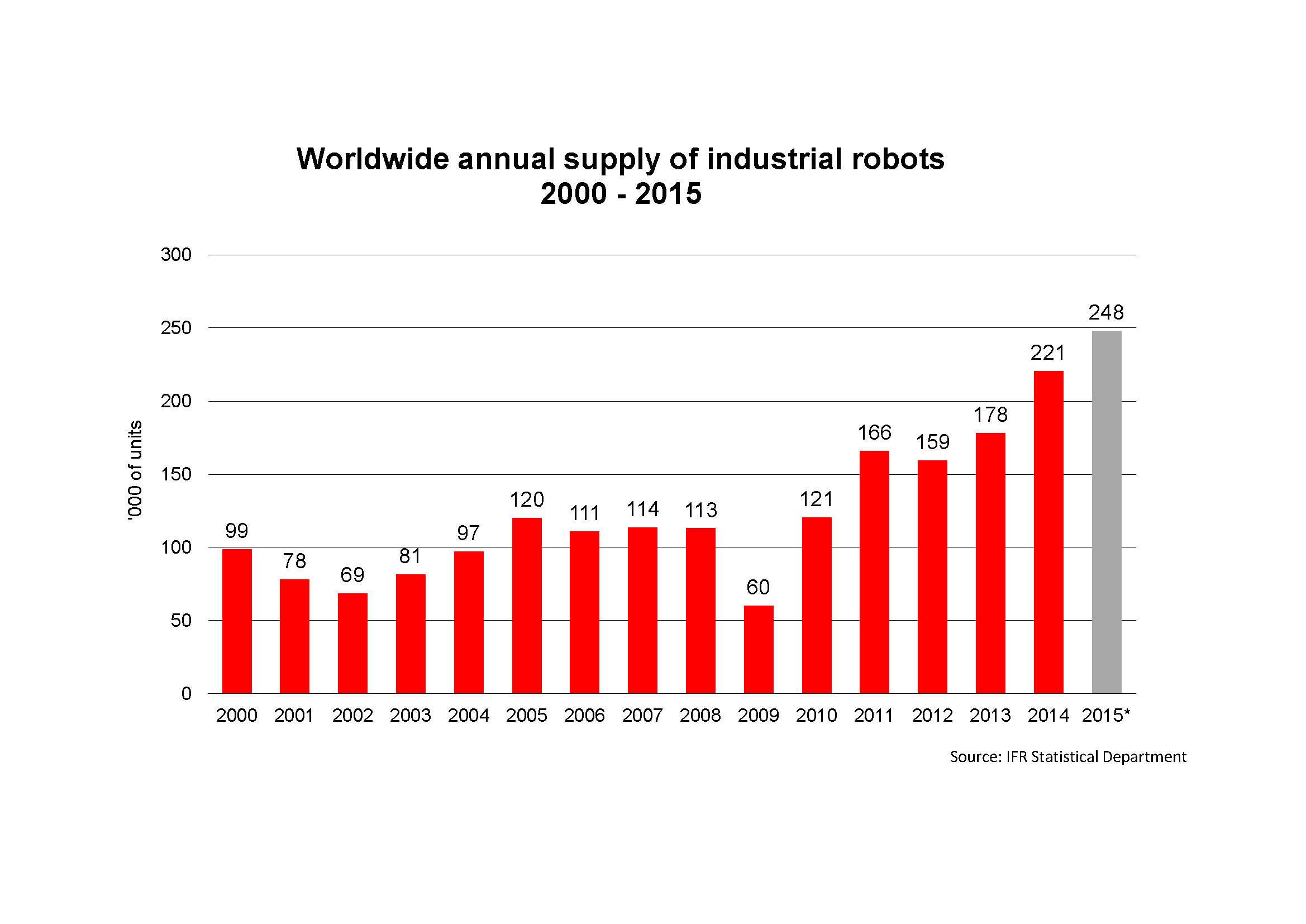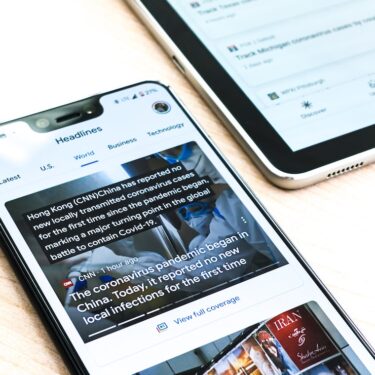■「精神の健全性」が大事 残っていれば改革は成就
韓国経済は、1997年アジアの通貨危機をもろに受けてIMF管理となった。もがき苦しみながらもIMF管理体制を卒業して高度成長軌道に乗って隆々としていた頃、日本経済は失われた10年といわれデフレ経済から脱出できずにもがき苦しんでいた。当時の韓国のマスコミの論調では、日本経済の衰退論が盛んであった。
これと同じようなことが1970年代の日本のマスコミ界にもあった。日本経済が高度成長期を駆け登っていた頃、世界一の覇権国だった英国の凋落をみて日本のマスコミ界は英国病という用語を作った。16世紀に太陽が沈まない国とまでいわれたスペインの無敵艦隊を破ったエリザベス女王の英国は、その後にナポレオン戦争にも勝利して世界の覇権国となった。軍事だけでなく政治経済・文化にも秀でていた英国はまさに覇権国だった。
20世紀に入り、英国は第1次大戦でドイツのカイザーを退け、第2次大戦ではドイツのヒットラーに勝ったものの、経済的打撃は大きく、米国に多大の借金を残した。大戦後のスエズ動乱を境にして完全に覇権国から降りた。60年以降、基幹産業の国有化や社会保障費の負担増加にあえぎ、既得権益のいざこざで経済、社会問題が多発した。その結果、勤労意欲も陰りが見えたようだった。
当時の日本経済は昇り坂を駆け上っていく勢いがあった。日本のマスコミ界はそのような英国の状態を称して英国病という用語をつくった。
自分が隆々と昇り調子の時にそこにとどまっていたり、少しスローに下っている他者を見ると、立ち上がれないほど衰退していくように見えるものだ。よしんば、見た通りに衰退の道を歩いていたとしても、歴史を通して形づくられてきた文化や国家性まで掘り下げて見ることが歴史を学ぶということである。衰退を揶揄することでなく、衰退の因を表面的にのみ分析するのでもない。
日本経済がジャパン・アズ・ナンバーワンといい気になっていたバブル期に、英国でサッチャーが登場し、大ナタを振って見事に社会保障者などの圧縮により小さな政府をつくった。現在覇権国ではないが戦後の凋落から立ち直り、世界の一流国となっている。
国の勢いがなくなり、そのまま後退してしまう国もあるが、復活する国もある。その違いは国民の精神の健全性にあるといわれる。精神の健全性が残っている間は改革が通用する。それが無くなってしまうと、改革をいくら唱えても、それぞれの人の利権の声でかき消されてしまう。
80年代に日本で大企業病という用語がつくられた。大企業にありがちな悪い風習という意味である。会社の強みがおごりにつながり、自分一人くらいダラケても影響ないなどの空気感のことである。創業当時の企業は、社員一人一人が目標に挑戦し成果を祝う。企業は成長の坂を駆け上り、大企業への軌道に乗る。しかし、その過程で大企業にありがちな悪しき風習が漂っていることを感じたリーダーが改革を断行し、軌道を再び成長にもどしたのが大企業病という用語の語源であった。
成長当時は、企業にはまだ健全な精神が残っているから改革が成功するのである。企業を構成する社員が大企業病にかかると次のような特徴が現れるという。セクションの壁がどんどん育つ。検討をするがまずやってみることがない。足りないものに目が行く。現状維持に固執する。現場と乖離した通論を唱える。などのことである。これらの兆候が現れているとしても成長しようという意欲や勤労意欲の精神が残っていれば改革は成功することを歴史は教えている。

 オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。
オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。