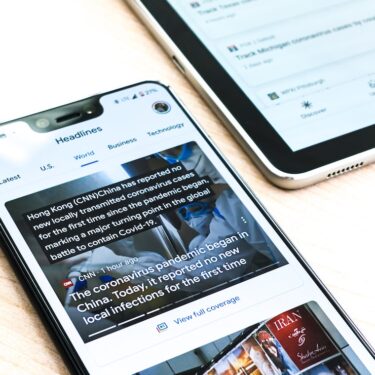受け取ってからの対応 重要
さて、筆者の趣味の一つが読書で、特に日本の大衆小説を好んで読むのですが、知的財産をテーマとした物語に出合うことはほとんどありません。そんな中、2011年に直木賞を受賞した池井戸潤氏の企業小説「下町ロケット」は、特許権が物語の大きなキーとなっており、後にテレビドラマ化もされ話題となりました。
本作は主人公が経営する小企業「佃製作所」と重工業会社との間に生じた軋轢を題材にしたもので、重工業会社が開発する宇宙ロケットの心臓部にあたるエンジンの燃料系バルブをめぐる争いの中で、最終的には「佃製作所」が保有する特許が決め手となり、ほぼハッピーエンドで終わっています。社会通念上の弱者の立場から正義を追求する、池井戸氏ならではのストーリー展開です。
この物語に登場する重要人物「神谷弁理士」の実在モデルとされる鮫島正洋氏(弁護士・弁理士)は、あるメディアのインタビューで「中小企業にとって知財が役に立つという事例は結構あるのか?」という質問に対して、「小説ほど劇的な事例はなかなかないが、知財が役に立たないかというと全くそんなことはない」と述べています。
この「全くそんなことはない」という言葉にはどんな意味があるのでしょうか。企業秘密を扱う法律家の立場から具体的な事例に言及することは避ける一方、たくさんの事件を扱った経験から「いろいろなレベルで知財が役に立った事例がたくさんある」ということをこの言葉で表現しているように思われます。
一般に、知的財産がらみの争いは、少なくとも訴訟に至るまでは表に出ることはありません。しかしながら、世界的な規模では、第三者の目には見えない水面下で幾千もの争いの火種がくすぶっていることは周知の事実です。
自社の知的財産が模倣などにより侵害されていることが明らかになった場合、その会社がとるアクションの第一段階は「警告状」(letter of warning)を自社あるいは代理人名で侵害被疑者に送りつけることです。知的財産の世界では、この警告状を「ラブレター」と呼んでいます。このようなラブレターの書き方にもいろいろな流儀やパターンがあるようです。
そのパターンの一つは、「貴社の製品○○は弊社の特許◇◇を侵害しているので製造・販売を直ちに停止されたい」という趣旨のみを記すものです。製品のどこがどう特許に抵触するのかなどの詳細を書かず、相手方に研究させるというやり方です。しかし、このようなやり方が世界中どこでも通用するかというと、そうではありません。十分な根拠や証拠を示さずにラブレターを送りつけると、そのような行為自体が違法であるとされる国もあります。例えば台湾などです。
日本の大手企業の場合、ほぼ毎週のようにこのようなラブレターを受け取るようです。受け取った企業はいろいろな対策を講じますが、まずは侵害されているとされる相手方の特許の分析が必要となります。後々訴訟に至った場合、国によっては「警告状を受け取った段階で侵害の可能性を認識していた」とされ、万一敗訴した場合の賠償金額に影響するので、迅速な対応が必要です。
中国はアメリカを上回る訴訟大国です。筆者の勤める知財コーポレーションでは、中国における知財裁判の開廷情報を速報で届けるサービスを提供していますが、全国の裁判所には毎日数百件の知財裁判(多くは内国人間の商標や著作権をめぐる争い)が提起されています。中国に進出した日本企業が中国企業からラブレターを受け取ることも多いようですが、そのような場合、的確な情報収集が必要なことはもちろんですが、優秀な現地代理人の起用と正確な翻訳が重要となります。
「下町ロケット」のように爽やかなエンディングばかりではありませんが、知的財産をめぐる多彩な物語が今日も世界中で繰り広げられていることでしょう。
◆清野安希子(きよの・あきこ)
国際基督教大学教養学部卒業。教育関連企業勤務を経て、2002年に知的財産専門翻訳会社の知財翻訳研究所(13年に知財関連サービスの拡充に伴い知財コーポレーションに社名変更)に入社。2年間の事務職勤務の後、営業担当として日本全国の大手メーカー知財部とのコネクション構築に注力。15年に中小企業診断士登録。現在は経営企画室長として事業戦略の立案や新規事業開発に携わっている。

 オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。
オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。