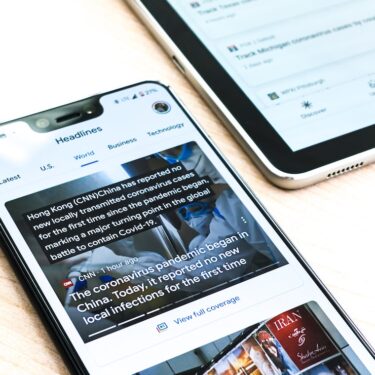これが究極の売り方だ、なんていう売り方は機器部品の営業にはあり得ない。平成期の中頃に、そのような売り方があると錯覚した営業人がいても不思議ではなかった。機器部品の売り方は、一般の営業とは多少違った特色を持っているからそのような発想が生まれた。日本の製造業が成長拡大した昭和期は、とにかく先へ先へと駒を進めた。そのために製造設備やラインは粗削りのまま急造される状況だった。
平成期には超円高が引き金となって、国内での生産拡大は止まった。この時期に今まで粗削りのまま急造してきた設備やラインがじっくり見直された。現場ではFA技術に磨きをかけて、品質向上や製造原価低減を図って設備やラインの改善に全力を挙げてきた。そこで使用される機器や部品も、現場からの要請に応じて品質向上やコストダウン、あるいはいろいろな機能を追加したシリーズ品が発売された。
販売面では、平成期の国内設備が昭和期のように増加拡大しなかったために販売競合が一段と激しくなった。このような状況下で、なぜ究極の売り方論が出たのだろうか。
昭和の成長拡大期では次々と機器や部品が誕生した。それらの商品を採用するマーケットも広がった。販売店では機器や部品が飛ぶように売れていき、売れていった機器や部品は、顧客ではどんな箇所にどんな役割で使用されているのかがわからないまま売り上げは伸びた。そのような状況は平成期に一変した。
売り上げは思ったように伸びずに競争は激化の一途をたどった。競争に勝つため、品質向上や機能に特色を持たせたシリーズ品を次々と発売し、競合切り替え営業を展開してきたのが平成期の営業であった。そこで考えたのが商品の差異化プラス売り方の差異化だった。昭和の“行け行けドンドン”の時代から、機器や部品が設備や機器のどんな所にどんな役割で使われているかわからないまま売れてきた。これがわかれば現場に出向き競合に先んじて有利な営業ができる。そのように考えて、知り得る全ての設備や機器のどの箇所に機器部品が使われているのかを調査し、競合優位を解説した売り方集が作られた。そして競合優位とアプリを勢力的に勉強して、該当する現場へ競合より早く出向き営業活動をした。これこそが競合に先んずる究極の営業と思ったのだ。
しかし、販売員の負荷の割にはそれほどの効果は見えなかった。その上、令和の販売員にとって落とし穴が待ち構えていた。
その一、FA分野の機械装置やライン設備は、品質向上、生産効率向上や環境・安全の面で改良、改善される。それに応じて機器部品もいろいろな機能を加えたシリーズ品を発表する。だから機器部品のアプリはそれほど大きく変わらないという前提に立っている。平成期は確かに大きく変わらなかったが、令和期は材料技術や要素技術の大きな飛躍がある。その技術は、機械装置やライン設備を一変し生産構造が変わるだろう。一例を言えば、産業技術総合研究所で進めている半導体製造装置であるミニマルファブのようなものである。機器部品のアプリも新しくなる。
その二、FA製造ラインにICT技術が大きく関わる。レイアウトフリーや工場内の管理がどんどん自動化される。その場合に機器・部品自体が変わるし従来にないアプリになる。
これだけでも究極の売り方などないことがわかるが、さらにその三、平成の営業人が言った究極の売り方を身につけてしまうと、令和の販売員はダメになってしまう。理由は、販売員とはマーケットに対して研ぎ澄まされた感覚を常に磨いていなければならないのに、大変な研修や勉強を強いられて覚えた売り方を身につけてしまうから販売センスがなくなる。そもそも機器部品のアプリは教えられて売り込むものではなく、販売員が自ら発見するものなのだ。

 オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。
オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。