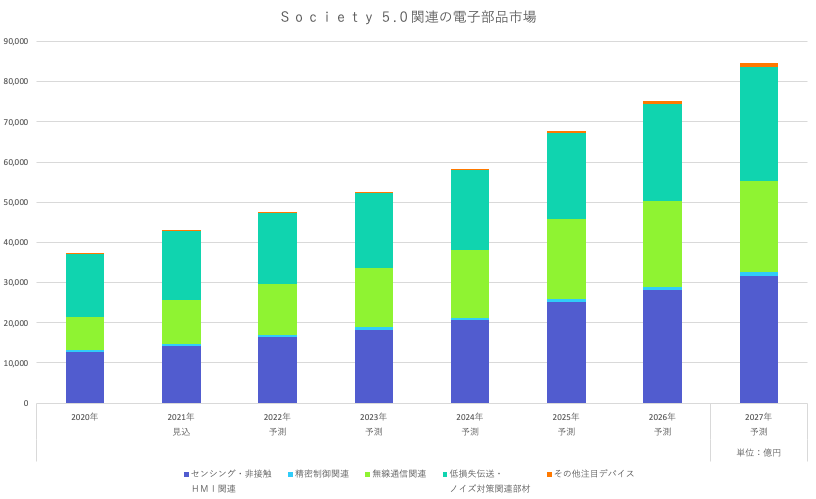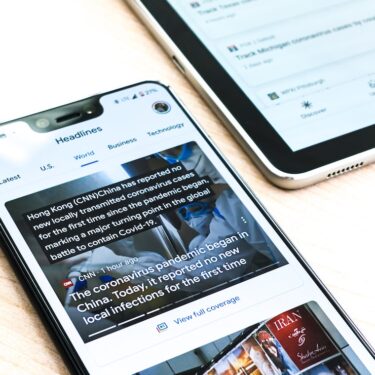「すべての道はローマに通ず」この言葉はなかなか厄介だ。
もともとは、17世紀、フランスの詩人ラ・フォンテーヌの「寓話」のなかで、魂の救済という同じ目的を目指した3人が、結果として裁判官と修道士と隠者という別々の道を選んだことを「All road leads to Rome」と評したのを言葉の由来としている。同じところを目指したはずなのに道は分かれた。でも、それぞれに目指すところは同じであり昔から変わっていない。このことをもって「手段や方法は一つではなくいくらでもある」「何をしても結局はひとつの答えに行き着く」と正反対の意味を2つもつ厄介なことわざになってしまったが、個人的には、目的を明確にすることの重要性を刻むための言葉だと理解している。
いま社会の仕組みが複雑化して先行きが見通せない時代だ。さらに、情報が氾濫し、物事の本質を掴むことが難しくなっている。そのため枝葉に気を取られ、物事を前に進めにくくなっている。製造業においても、企業としてやらなければいけないこと、やった方が良いこと、やらないこと、やってはいけないことの境界線が曖昧になり、その選別や判断に迷うことが増えてきている。言うなれば、枝葉である部分最適が過度に進み、全体最適が進まない。特にDXを巡る文脈ではそう感じる。DXの目的または実現した姿を、変革して企業風土を変革するという論調をよく目にするが、それは間違いだ。変革した後にどうなるか、企業にとってどういう姿が理想であるかを描き、そこに向かっていなければ何の意味もない。
そんな今だからこそ改めて「すべての道はローマに通ず」という言葉の意味を考えてみたい。どんな手段も方法も道のりもひとつのゴール、目的地があってこそ。ゴールからコースは生まれ、ゴールに向かってレースは集約していく。製造業の企業のゴールは、どれだけ時代が変わっても「利益創出」以外にはあり得ない。売上を増やし、利益を上げることができてはじめて市場に価値を還元し、従業員の生活を守り、雇用を産み出し、地域社会に貢献できる。DXを実行してもそこで利益を生めなければ意味がなく、整備したシステムも人材も、新しい会社文化も単なる箱でしかなくなる。「すべての道はローマに通ず。すべての業務は利益に通ず」これを実現できるDXが本物のDXだ。

 オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。
オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。