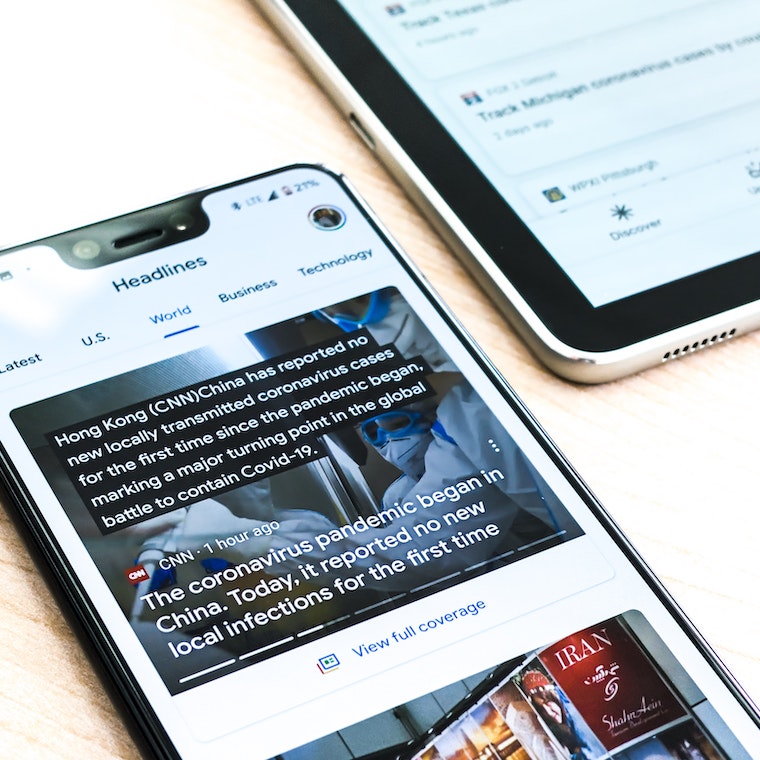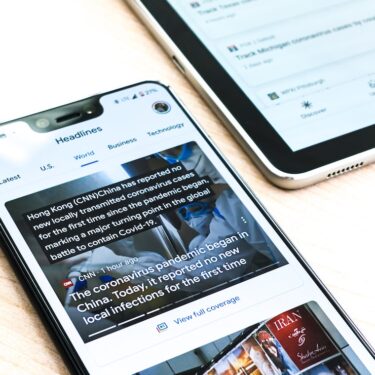世の中の変化のスピードは加速し、また地政学的リスクが高まる昨今。過去の成功事例や経験だけでは、技術系企業も生き残れない。そのような危機感は多くの技術系企業において共有されていると感じます。各社がこの苦境を脱するために様々な行動を起こしていますが、その一つが異なる技術を有する企業との協業、いわゆる異業種協業です。
この異業種協業を行うにあたり、企業のマネジメントは何を考え、技術者育成の観点でどのような教育を行えばいいのか、というのが大変重要になってきます。ここでは異業種協業のうち技術的観点に着眼し、異業種技術協業として技術者をどのように誘導すべきかについて考えていきたいと思います。
異業種技術協業の考え方は既に一般的になりつつある
異業種協業という単語を検索すると、540,000件のページがヒットをする時代です(2022年4月現在)。自社技術や製品のコモディティー化、既存市場の終焉といったキーワードをちりばめながら、今あるものの地盤沈下や変化が異業種協業を後押しする、という論調が主流のようです。
特に異業種協業の際にポイントとなるのは、技術の交流。すなわち異業種”技術”協業です。この考え方は欧州では比較的盛んです。一例がコンソーシアムというシステムです。コンソーシアムでは川上、川中、川下という異なる位置にいる企業が、異なる技術を持ち合いながら出口戦略まで含めて技術的業務を完結させる、という取り組みが根底にあります。
よって、日本が得意としてきた高効率を実現する徹底した縦割りではなく、異業種技術交流によって従来にない付加価値、より具体的には課題解決できる製品を創出する、というのが時代の主流になりつつあります。それでも何かしらの具体的な技術のキーワードが欲しい、補助金などが出やすいテーマを構築したい、という欲求は多くの企業にあり、自動化、AI、DX等のキーワードに向けた取り組みを加速する企業が最近増加した背景となっていると考えられます。
異業種技術交流では顧客を得るという考えだけでなく、自らが顧客になるという姿勢が大切
当たり前といえば当たり前ですが、異業種技術交流に参加するほとんどの企業が、「自社の技術や製品を使う顧客を得たい」という意識があります。しかし、全社がこの考え方だけではどのようにして自社技術や製品を使ってもらうか、
売ってもらうかという所に意識を集中すると、異業種技術協業で最も大切な、「協業により、従来にない付加価値、より具体的には課題解決できる製品を創出する」という”協業の視点”が失われてしまいます。
これでは、異業種技術協業ではなく単なる交流で終わってしまうでしょう。このようにならないために必要なのは、「顧客を得るという考えだけでなく、自らが顧客になるという姿勢」です。この考えを、川上、川中、川下のどの領域にいる企業も持つことが求められます。Give and Take という前提を成立させないと、お互いが本当に力になりたいと協力しようというスタートラインに並べないのです。
従来の縦割りで進められていた時代は、川下企業がどのような技術が欲しいのかという、顧客としての取りまとめのような役割を担っていました。それを受け、川中、川上と技術的な要求等が遡上していきます。ただこの流れは、川下における方向性の変化により大きく変動することもあり、場合によっては突然中止となるなど、リスクが生じやすい仕事とも言えます。さらに市場の要望が多様化した今、川下企業だけでは「従来にない付加価値創出」というところまで到達できない時代になってきています。
このような背景も踏まえ、川上、川中の企業も川下からのニーズを待つだけでなく、同じテーブルで議論を交わすという姿勢が不可欠です。自らの企業が川中や川上にいたとしても何かしらの課題はあるはずです。その課題を踏まえ、どのようにして解決に向かうかという点において、他の企業の技術を応用できないかという考え方が上記のテーブルに座る前提条件であり、すなわち異業種技術協業の肝となります。
自社技術の課題解決力、自社に足りない技術を求める技術要求力の両輪で情報を発信
異業種技術交流に参加するのは技術者たちです。その技術者が行うべきは2点です。それぞれについて述べます。
■顧客を得ようとする場合にポイントとなる技術者の事前準備
一つは、顧客を得るための観点です。そこの観点で求められるのは、「自社技術でどのような課題が解決できるのか」ということです。課題例とその解決事例を示すことで、潜在的な顧客に課題解決のイメージを持ってもらうのが重要です。
その際は、・定性的ではなく、できる限り定量的な結果を示す・比較対象となる従来製品や従来技術との違いを示す・字だけでなく、画像やグラフを活用する、ということがポイントになります。
■自社が顧客になる場合に必要な技術者の事前準備
もう一つの観点が、自社が顧客となる観点です。こちらが盲点となっているケースが多いといえます。この観点で求められるのは、「実際に課題と感じていることをできるだけ実例を用いて明確に示す」ということです。ここでは、・具体的に課題と感じている事象、事実・現段階でその課題解決に有効と考えている対策案、という2点が述べられているのがポイントです。
当然ながら、定量的かつ画像やグラフを用いて説明できる方が望ましいということになります。このような2種類の観点を事前に準備し、それを技術者がきちんと説明できるようにしておく、ということが異業種技術協業を成功に導く必要条件です。そしてこちらも当たり前ですが、自分たちの話だけでなく異業種技術を有する企業の話を聞き、その企業に歩み寄るという柔軟性も必須です。
いかがでしたでしょうか。異業種技術協業というと、自社が顧客を得る、という観点だけになりがちですが、それでは協業ではなく一方通行になります。自社も顧客になるつもりがあるという視点に加え、未知の技術を理解し、理解しようとする歩み寄りも大変重要です。異業種技術協業には、お互いの企業やその技術に対する配慮や経緯が生命線になる。この前提をきちんと理解した上で異業種技術協業に取り組むことが肝要です。
【著者】

吉田 州一郎
(よしだ しゅういちろう)
FRP Consultant 株式会社
代表取締役社長
福井大学非常勤講師
FRP(繊維強化プラスチック)を用いた製品の技術的課題解決、該関連業界への参入を検討、ならびに該業界での事業拡大を検討する企業をサポートする技術コンサルティング企業代表。現在も国内外の研究開発最前線で先導、指示するなど、評論家ではない実践力を重視。複数の海外ジャーナルにFull paperを掲載させた高い専門性に裏付けられた技術サポートには定評がある。
https://engineer-development.jp/

 オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。
オートメーション新聞は、1976年の発行開始以来、45年超にわたって製造業界で働く人々を応援してきたものづくり業界専門メディアです。工場や製造現場、生産設備におけるFAや自動化、ロボットや制御技術・製品のトピックスを中心に、IoTやスマートファクトリー、製造業DX等に関する情報を発信しています。新聞とPDF電子版は月3回の発行、WEBとTwitterは随時更新しています。